多田精機グループは、高度な金型技術を基盤に、社会に貢献できるものづくりを追求しています。持続可能な社会の実現に向け、技術革新に挑むとともに、地域社会との連携を深め、次世代を担う人材の育成にも力を注いでいます。
金型は、お客様の事業を支え、ひいては社会全体の発展につながる。そんな想いを胸に、未来の技術発展と豊かな社会を支えるさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。
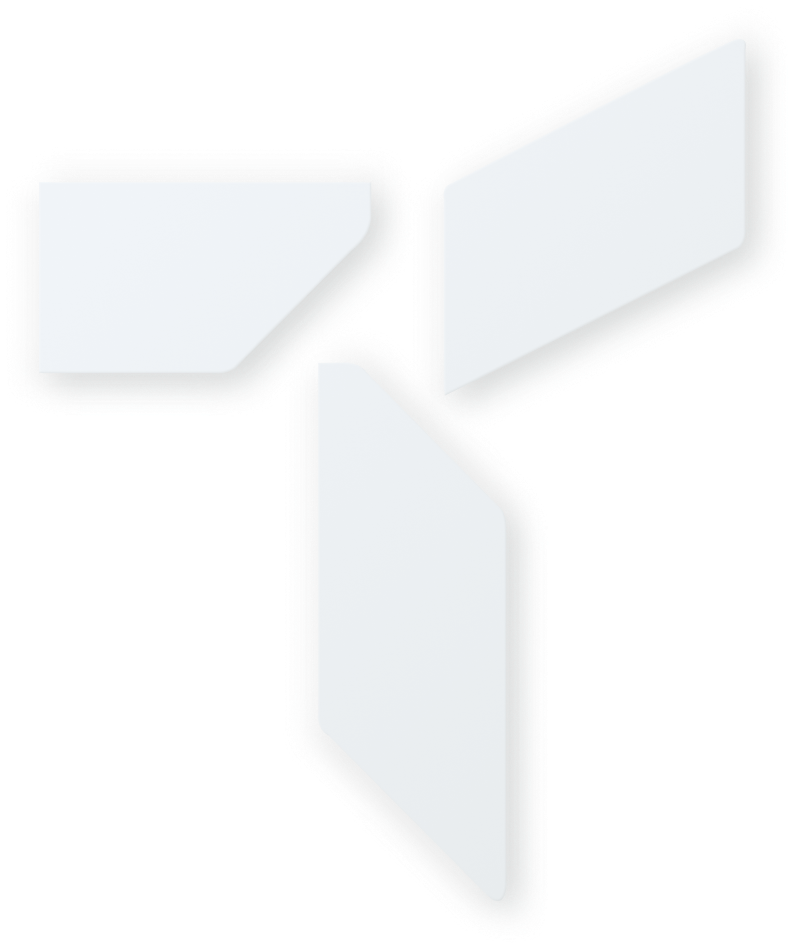

多田精機グループは、高度な金型技術を基盤に、社会に貢献できるものづくりを追求しています。持続可能な社会の実現に向け、技術革新に挑むとともに、地域社会との連携を深め、次世代を担う人材の育成にも力を注いでいます。
金型は、お客様の事業を支え、ひいては社会全体の発展につながる。そんな想いを胸に、未来の技術発展と豊かな社会を支えるさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。
製造業を取り巻く環境が大きく変化する中、県・岐阜大学と連携し、IoT技術を活用した次世代金型「スマート金型」の開発に着手。不良品削減や生産性向上、省人化といった課題解決に貢献するため、産学連携による新たな挑戦が始まりました。
岐阜大学および複数の民間企業と共同で「スマート金型開発拠点」を設立し、金型内部の温度や圧力、歪みなどをリアルタイムに計測できるセンサーを組み込んだ金型の開発に取り組みました。計測されたデータはIoTプラットフォームを通じて収集・解析され、自律的な成形条件の最適化を目指します。この「スマート金型」により、熟練技能者の経験と勘に頼っていた成形条件の調整を、データに基づいて行うことが可能になりました。
岐阜大学スマート金型開発事業拠点に参画する企業(抜粋)
株式会社岐阜多田精機、オムロン株式会社、株式会社デンソー、扶桑工機株式会社
金型内部の情報をリアルタイムに把握し、収集・解析することで、成形条件の最適化に向けた知見を得ることができました。これにより、不良率の低減、生産性の向上、省人化を実現し、地域産業の振興に貢献することが期待されています。
自動者産業では、シフトノブやスイッチなどの内装部品に対する高いデザイン性と低コスト化が求められていました。
海外の自動車デザインが注目される中、日本メーカーも高級感のある内外装デザインを実現する新技術を模索していましたが、従来の加飾方法(フィルム貼付や水圧転写)では、複雑な曲面への対応が難しく、工程が多いためコストが高くなるという課題がありました。
レーザーアブレーションにより微細な模様を彫り込むことで複雑な立体形状を実現。
そして、レーザーによる立体模様を一次成形し、その上に重ねるように透明な樹脂を二次成形することで自由度の高い加飾が可能になりました。
樹脂の厚みの差による光透過率の違いで色調変化を表現したり、幾何学模様や写真画像の再現など、様々な応用が可能です。
さらに樹脂の流動解析や配合技術を研究し、薄肉成形でも均一な仕上がりを実現しました。
共同研究者
岐阜大学、岐阜県産業技術総合センター
デザイン性や品質の高い加飾を可能にしただけではなく、コスト削減・環境負荷軽減にも大きく寄与しています。
プラスチック成形品の従来の加飾方法では、塗装にかかる時間や人的コスト、溶剤が必要ですが、射出成形の段階で塗装が完了するためコストを大幅に削減できます。
自動車メーカーだけでなく、住宅設備や家電メーカーからも注目され、他分野への応用が期待されています。
自動車製造の一大拠点として成長するインド。その一方で、圧倒的に不足する金型技術。
当社がJICA(国際協力機構)の民間連携事業に参画したのは、まさにその課題に挑み、現地製造業の技術力向上に貢献するためでした。
JICA(国際協力機構)の民間連携事業を活用し、インドの現地エンジニア育成プログラムを実施。設計・製造ノウハウを凝縮した「モジュール金型」を教材として提供し、現地パートナー企業と共有することで、高品質な金型供給体制の構築を目指しました。教育カリキュラムを修了した人材は、現在、インド各地で金型の指導者として活躍し、日本式金型技術の普及に貢献しています。
単なる技術支援に留まらず、現地経済の発展と日系企業支援という、二つの大きな目標を掲げて推進されたプロジェクトでした。
インド国内においてこれまで対応できなかった高度な金型に関する相談や発注が増加し、ビジネスチャンスが大きく広がりました。日本式金型技術がインド製造業全体の技術レベル向上に貢献すれば、現地に進出する日系企業への強力なサポート体制が構築されることも期待できます。
多田精機グループの技術とノウハウがインドの製造業の発展に貢献できたことは、今後のさらなる事業展開への大きな足掛かりとなることでしょう。
岐阜県立岐南工業高校の生徒が考案した「ゆで卵の殻むき器」は、そのユニークな発想で注目を集めましたが、何百万円とかかる金型製作費用の問題から商品化が困難に。地域社会への貢献を理念とする多田精機グループは高校生たちの熱意に共鳴し、その夢を実現するための支援を決意しました。
岐阜県主催のプレゼンテーション会で高校生のアイデアに感銘を受け、金型製作を全面的にバックアップ。高度な金型技術を駆使し、試作金型の製作から量産化までを支援しました。高校生たちの自由な発想と、当グループの技術力が融合することで、地域社会に貢献できる新たな製品の創出を目指しました。
高校生のアイデアを製品化するための金型が完成し、ゆで卵の殻むき器は、製品名「つるっとたまご」として販売会を開催。岐阜市役所や岐阜県内のスーパー・ショッピングモールなどで販売会が開催されたほか、道の駅やカフェなどでも委託販売が行われました。
\Check/
『ナニコレ珍百景』で紹介されました!
テレビ朝日系列『ナニコレ珍百景』に取り上げていただきました。高校生の熱意と当グループの技術が融合した取り組みを、ぜひチェックしてみてください。
持続可能な社会の実現に向けては、脱炭素社会への移行が喫緊の課題となっており、そのためには再生可能エネルギーの導入拡大と、電力の変動に対応する蓄電技術の確立が不可欠です。
しかし、一般的に用いられるリチウムイオン電池には、熱暴走や発火のリスクに加え、充放電を繰り返すことで数千サイクルで容量が低下するという課題があり、長期運用に適した蓄電池とは言えません。
当社が開発するレドックスフロー蓄電池は、高い安全性と長寿命性を兼ね備えており、余剰電力を安定的に蓄え、有効活用するシステムとして大きな期待が寄せられています。
当社が開発するレドックスフロー蓄電池は、酸性の水溶液を使用する特性上、金属部材では劣化の恐れがあるため、カーボンや樹脂といった耐腐食性の高い材料の採用が不可欠です。
樹脂部品には、当社の高精度なプラスチック射出成形技術を、またカーボン部品には、独自のカーボン電極切削技術を活用することで、低コストかつ高機能な蓄電池部材の製造が可能となっています。
これにより、高性能・高寿命・低コストを兼ね備えたレドックスフロー蓄電池の製造を実現しています。
当社が取り組むレドックスフロー蓄電池の開発は、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。
この電池は、再生可能エネルギーによって生まれる余剰電力を蓄電し、有効活用することが可能であり、さらに停電時の非常用電源としても活用できます。
また、工場における電力使用のピークカットによるコスト削減にもつながり、金型製造業においても競争力のある生産体制を構築することが可能です。
加えて、クリーンエネルギーを活用した製造体制の構築は、環境配慮が強く求められる現代社会において、当社の金型製品の営業活動にも大きな付加価値をもたらすと考えています。
グローバル規模での価格競争が激化する現代において、効率化と技術革新は不可欠です。多田精機グループでは、社会全体で推進されるDXを課題克服と成長の機会と捉え、生産現場におけるIoTやAI技術の活用を積極的に推進しています。
以下の取り組みを通じてDXを推進しています。
主な取り組み
生産ラインの稼働率が向上し、不良品発生率が低減するなど、コスト削減と競争力強化につながっています。将来的には、海外工場への金型貸し出しや、DXによる働き方改革も視野に、技術革新と社員の成長を目指したいと考えています。